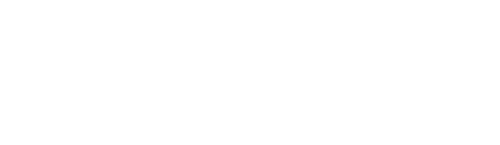「持続可能性」を教えるとはどういうことか -非認知的能力考-山田肖子
2020年に導入された日本の新学習指導要領では、「持続可能な社会の創り手」である児童・生徒たちがこれからの時代を担っていくための(1)知識・技能(2)思考力・判断力・表現力等(3)学びに向かう力・人間性等をはぐくむことの必要性が謳われている。こうした知識・能力は、数学の公式や歴史上の出来事を暗記するのと違い、どういう行動を取ることが「持続可能な社会」を創ることにつながるのかを判断できなければ発揮できない。また、社会が「持続可能」になる条件は、状況によって異なるため、「どの科目で何を教えればよい」といった明確な決まりがない。つまり、生徒、教師の双方にとって、分かりやすい正解がなく、状況対応型の判断を求められるものが、学習指導要領の随所にちりばめられたと言える。
日本の文部科学省は、ESD(Education for sustainable development:持続可能な開発のための教育)を提唱し、ユネスコが実施した「持続可能な開発のための教育の10年(2004~2014)」を資金及び実践の両面でバックアップした。2014年11月には、この10年を総括するユネスコ世界会議を日本に誘致し、ESDの継続を謳った「あいち・なごや宣言」が採択されている。また、2015年に国連本部で採択されたSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)の第4目標(すべての人に質の高い教育を提供する)の一部に”Education for Sustainable Development”という文言が盛り込まれたのも、日本の外交努力の結果に他ならない。
2000年代以降、ユネスコ・スクールやスーパー・グローバル・ハイスクールに認定された中・高等学校などで、このESDが様々な形で行われてきたことは素晴らしい成果である。また、私はESDの専門家でもなく、その教え方や成果について語る立場にはない。しかし、ESD=「持続可能性を教えること」ではないように感じている。ESDの実践例は多様だが、環境問題、途上国の貧困や社会格差など、他者の置かれた状況について理解を深め、共感する気持ちを養おうとするものが多いのではないだろうか。それはとても重要なのだが、教育関心の高い家庭のよくできた子どもたちが、自らの切実な実感を伴わずに学ぶ教養的なものになってしまっていたとしたら、それは「持続可能な社会」の本質とはまた違う、ESDという営みなのではないかと思う。
「持続可能性」という1980年代に生まれた造語が、現代において何を意味するようになったかは、別稿で詳しく述べたいが、ここでは、実感を伴う「持続可能な社会」で生きるための能力とは何か、またその能力が身についたかどうかを客観的にとらえることができるのか、という観点から論じたい。
実感を伴うためには、その能力は、それを身に付ける人にとって、日常に根差している必要があるだろう。つまり、今日、接する友人や家族、通勤や通学の途中ですれ違う人々、風景の中にある建築物や自然物、食するもの、使う道具…。そうした身近なものや人、環境に興味を持ち、関わる態度や行為が、「持続可能な社会」で生きるための能力の形成につながるのだろう。
「持続可能性」とは、非常に道義的な内容を含む言葉である。つまり、地球の資源であれ、人間社会の政治的、経済的、文化的活動であれ、我欲を一方的に追及していては「持続」しないので、調和的な発展のため、欲望を抑える態度や行為が必要だ、ということである。他者に配慮する、モノを大事にする、といった道徳は、どのような社会にも存在してきた。しかし、グローバル化し、ある社会が世界から切り離された閉鎖空間であることはほとんど不可能になった現代において、道徳というものもグローバル化したということか。しかし、道徳の概念がグローバル化したからと言って、人々の日々の暮らしから離れた態度や行為を学校で教え、さらにそれが児童・生徒の身体に内面化されるのを見届けるのは難しいだろう。
例えば、授業で、日本の家庭で毎日飲まれているコーヒーは、遠い国の子どもの労働を搾取して収穫されているので、児童労働を撤廃しなければならない、と学んだとしよう。それは「知識」として意義深いが、その授業を受けた児童・生徒が、夕飯のカレーに入っているジャガイモを見て、「日本のジャガイモ農家さんの子どもは家業を手伝ったりするのかなあ。楽しいからかなあ、無理やりかなあ?」と考える可能性は低いかもしれない。強制されずに自らの意思で手伝っていれば、それは児童労働ではないのだが、もし遠い国の誰かがそうせざるを得なくて労働しているとした場合、楽しくて手伝っている子どもと何が違うのかを考えると、初めて遠い国の問題は自分につながってくる。しかし、同じ農作物の消費に関することでも、日常から切り離された“グローバル”な知識は、身近な問題に置き換える想像力を阻害しかねない。
「持続可能性」を教え、学ぶということが、実は身近なことから始まるのだとするなら、では、そうした教育が目指すような態度を児童・生徒が身に付けたかどうかはどのように把握すればいいのだろうか。教育とは、一定の知識や能力を身に付けた人材を養成することを目的に行われる介入であるので、結果が分からなければ、その介入が有効だったかどうかがわからない。しかし、「持続可能性」のための教育のような態度変容を促す教育は、結果を把握する方法が確立しておらず、「どんな介入をしたか」の事例ばかりが紹介されがちである。そして、日々仕事が多い学校現場の先生方も、すぐ使える教材や教案が欲しいとおっしゃることが多い。そうなると、身近なテーマより、大上段に構えた途上国の開発問題や環境汚染といった授業がどうしてもよく見えてしまうかもしれない。
名古屋大学SKY (Skills and Knowledge for Youths)プロジェクトが行っている若者の技能評価では、頭で理解する認知的な知識以外に、人間が物事を判断して現実の問題に対処する能力として非認知的能力というものがあるという考え方に立ち、非認知的能力を計測しようとしている。この計測では、「○○の状況で、あなたはどう行動するか」といった態度、行動に関する質問を数多く提示し、その回答傾向からその人が、どういう非認知的能力を持っているかを可視化する。我々はこれまで途上国の産業労働者が仕事の場で問題解決するために非認知的能力がいかに重要か、という観点から、こうした計測を行ってきた。そうした経験と視点を持って、昨今、日本で盛んな「持続可能性」に対する態度の教育が必要だ、という議論を見ていると、○○すべき、という教育制度を計画したり運営したりする側の発想が中心になっている気がする。そして、もし、子どもたちに「持続可能な」社会をつくる能力が備わるとしたら、そうした身構えた議論とは全く別の、ソーシャルメディアや日常生活の中での身近な経験からなのではないかと感じてしまう。